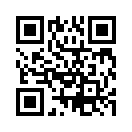2006年08月24日
スポーツと科学
毎日新聞
夏の甲子園が終わった。今大会は、早稲田実と駒大苫小牧の2日間にわたる壮絶な決勝の「記憶」と、本塁打量産の「記録」が象徴的な出来事として語り継がれるだろう。そんな二つの事柄に私は共通項があると見ている。高校野球の世界にも入り込んできた、高度なスポーツ科学だ。
21日の決勝再試合。午前中の試合前取材を終え、記者室に戻ってきた私は、同僚と取材内容を突き合わせていた。選手たちが語ったコメントをノートに書き込むうちに、「これはすでに勝負ありじゃないか」と思えてきた。早実の勝利をなんとなく予感したのだ。
前日には延長15回を戦っている。その夜に何をしたか、が重要なテーマだった。駒大苫小牧の選手は「スタミナが落ちないよう、ご飯を食べる量を増やした」「夜もティー打撃をして3箱のボールを打ち込んだ」という話をしていた。
これに対し、早実の和泉実監督は言った。「斎藤(佑樹投手)はかかりつけの先生にはりを打ってもらった後、高気圧のカプセルに1時間から1時間半は入っていた。私も入ったことがあるが、眠気が来て疲れがとれる。疲れると脳の働きにも影響があって試合でミスが出てしまうんです」
高気圧のカプセル、と聞いた時、私は「やはり」という気がした。というのも、前日の試合で奇妙な場面を目撃していたからだ。斎藤投手が走者に出て、3アウトチェンジでベンチに引き揚げてくると、控え選手が細長い缶を手渡した。その上部には小さいラッパのようなものが付いていて、斎藤投手はそこに口を当てた。携帯用酸素だった。
その光景を見て、宿舎ではもっとすごい疲労回復法をやっているのではと想像していたら、案の定、カプセルの話が出てきた。この中に横たわっているだけで酸素を多く摂取でき、疲労回復だけでなく、老化防止やケガの治療回復を早めるのにも役立つという。斎藤投手は4日連投でも球威を落とさず、九回には147キロの快速球を披露し、早実に初優勝をもたらした。
本塁打量産の理由は、最初のうちはよく分からなかった。しかし、次第に監督や関係者が語る内容はおおよそ一致してきた。
日本高校野球連盟の田名部和裕参事はこう説明した。「(01年秋の地方大会から)バットの重量を900グラム以上と決めたが、最初は重くて振れない選手が多かった。でも、去年あたりからよく振れてきたようだ。打撃マシンで速い球の練習を繰り返し、重いバットを振り抜く力がついてきたのでしょう」
別の関係者からは「多くの選手がプロテインなどのサプリメント(栄養補助食品)を取るようになってきた」という声を聞いた。好天続きでボール内側のウールから水分が抜けるため打球が飛ぶという説や、長雨の後の猛暑で投手のコンディション調整がうまくいかない、との分析もある。ただ、圧倒的に多い意見は、打者の筋力アップ説だ。最終的に大会通算記録を13本も上回る60本塁打。投打のバランスが乱れた大会でもあった。
酸素を摂取するためのカプセルはサッカー界では有名になっており、前イングランド代表主将、ベッカム選手が使っていたことから「ベッカムカプセル」とも呼ばれている。サプリメントを使った筋力アップも他のスポーツでは常識。高校野球は遅れていたが、徐々に浸透してきたようだ。
今、トップレベルのスポーツに科学は不可欠だ。そういう意味で、早実の優勝はグラウンド外も含めた総合力の勝利といえる。強豪校は今後、こぞってカプセルを探し、あの手この手で酸素の研究を始めるだろう。打撃の指導も、正しいスイングの技術以上にパワーアップに比重が置かれるかもしれない。
しかし、正確な知識と理解がなく、科学の力に頼る風潮ばかりがエスカレートすると、危険な世界と隣り合わせになる。むろん早実のケースはドーピング(禁止薬物使用)とは無縁だ。それは強調したい。ただ、五輪や欧州サッカー、米大リーグでは、酸素や筋力強化にまつわるドーピングが絶えない。03年静岡国体から国体でドーピング検査が導入されたことに伴い、日本高野連でも啓発活動を始めようとしている。指導者にはそうした知識習得が急務だろう。
すばらしい決勝戦。少しばかり見えてきたスポーツ科学の世界に、野球界も目を向けるべきではないか。熱戦の裏側を取材していて、そんな気がした。
==============
「記者の目」へのご意見は〒100-8051 毎日新聞「記者の目」係へ。メールアドレスkishanome@mbx.mainichi.co.jp
毎日新聞 2006年8月23日 東京朝刊
記者の目:早実優勝と本塁打量産の甲子園=滝口隆司(大阪運動部)
◇科学の知識と理解が必要--指導者の要件の一つに
夏の甲子園が終わった。今大会は、早稲田実と駒大苫小牧の2日間にわたる壮絶な決勝の「記憶」と、本塁打量産の「記録」が象徴的な出来事として語り継がれるだろう。そんな二つの事柄に私は共通項があると見ている。高校野球の世界にも入り込んできた、高度なスポーツ科学だ。
21日の決勝再試合。午前中の試合前取材を終え、記者室に戻ってきた私は、同僚と取材内容を突き合わせていた。選手たちが語ったコメントをノートに書き込むうちに、「これはすでに勝負ありじゃないか」と思えてきた。早実の勝利をなんとなく予感したのだ。
前日には延長15回を戦っている。その夜に何をしたか、が重要なテーマだった。駒大苫小牧の選手は「スタミナが落ちないよう、ご飯を食べる量を増やした」「夜もティー打撃をして3箱のボールを打ち込んだ」という話をしていた。
これに対し、早実の和泉実監督は言った。「斎藤(佑樹投手)はかかりつけの先生にはりを打ってもらった後、高気圧のカプセルに1時間から1時間半は入っていた。私も入ったことがあるが、眠気が来て疲れがとれる。疲れると脳の働きにも影響があって試合でミスが出てしまうんです」
高気圧のカプセル、と聞いた時、私は「やはり」という気がした。というのも、前日の試合で奇妙な場面を目撃していたからだ。斎藤投手が走者に出て、3アウトチェンジでベンチに引き揚げてくると、控え選手が細長い缶を手渡した。その上部には小さいラッパのようなものが付いていて、斎藤投手はそこに口を当てた。携帯用酸素だった。
その光景を見て、宿舎ではもっとすごい疲労回復法をやっているのではと想像していたら、案の定、カプセルの話が出てきた。この中に横たわっているだけで酸素を多く摂取でき、疲労回復だけでなく、老化防止やケガの治療回復を早めるのにも役立つという。斎藤投手は4日連投でも球威を落とさず、九回には147キロの快速球を披露し、早実に初優勝をもたらした。
本塁打量産の理由は、最初のうちはよく分からなかった。しかし、次第に監督や関係者が語る内容はおおよそ一致してきた。
日本高校野球連盟の田名部和裕参事はこう説明した。「(01年秋の地方大会から)バットの重量を900グラム以上と決めたが、最初は重くて振れない選手が多かった。でも、去年あたりからよく振れてきたようだ。打撃マシンで速い球の練習を繰り返し、重いバットを振り抜く力がついてきたのでしょう」
別の関係者からは「多くの選手がプロテインなどのサプリメント(栄養補助食品)を取るようになってきた」という声を聞いた。好天続きでボール内側のウールから水分が抜けるため打球が飛ぶという説や、長雨の後の猛暑で投手のコンディション調整がうまくいかない、との分析もある。ただ、圧倒的に多い意見は、打者の筋力アップ説だ。最終的に大会通算記録を13本も上回る60本塁打。投打のバランスが乱れた大会でもあった。
酸素を摂取するためのカプセルはサッカー界では有名になっており、前イングランド代表主将、ベッカム選手が使っていたことから「ベッカムカプセル」とも呼ばれている。サプリメントを使った筋力アップも他のスポーツでは常識。高校野球は遅れていたが、徐々に浸透してきたようだ。
今、トップレベルのスポーツに科学は不可欠だ。そういう意味で、早実の優勝はグラウンド外も含めた総合力の勝利といえる。強豪校は今後、こぞってカプセルを探し、あの手この手で酸素の研究を始めるだろう。打撃の指導も、正しいスイングの技術以上にパワーアップに比重が置かれるかもしれない。
しかし、正確な知識と理解がなく、科学の力に頼る風潮ばかりがエスカレートすると、危険な世界と隣り合わせになる。むろん早実のケースはドーピング(禁止薬物使用)とは無縁だ。それは強調したい。ただ、五輪や欧州サッカー、米大リーグでは、酸素や筋力強化にまつわるドーピングが絶えない。03年静岡国体から国体でドーピング検査が導入されたことに伴い、日本高野連でも啓発活動を始めようとしている。指導者にはそうした知識習得が急務だろう。
すばらしい決勝戦。少しばかり見えてきたスポーツ科学の世界に、野球界も目を向けるべきではないか。熱戦の裏側を取材していて、そんな気がした。
==============
「記者の目」へのご意見は〒100-8051 毎日新聞「記者の目」係へ。メールアドレスkishanome@mbx.mainichi.co.jp
毎日新聞 2006年8月23日 東京朝刊
Posted by やんち at 11:52│Comments(0)
│サプリメント